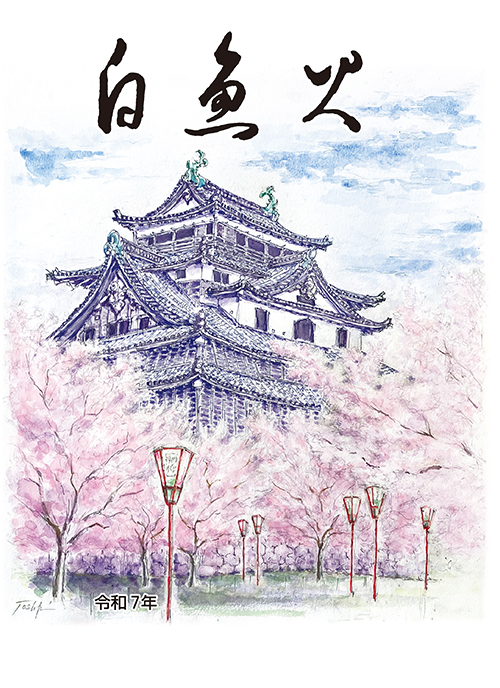|
梅雨 (出雲)安食 彰彦
万緑や銅剣里のまほろばに
三の丸ひとつばたごの花盛り
美しき若葉を挟む養生訓
気にかかる友の句集に柿若葉
余生とは暇つぶすこと梅雨に入る
休日や梅雨の海軍大社基地
梅雨冷の厨散らかし独り酒
なんとなく孫を呼びたる男梅雨
富士山 (浜松)村上 尚子
水木の花空を平らにしてゐたり
みづうみに雨見えてをり夏わらび
富士山の晴れ間短しさくらの実
茅葺きの屋根をかすむる夏つばめ
四十雀話のなかを通り過ぐ
黄菖蒲や筧より水ほとばしる
目に力入れて見てゐる青嶺かな
五月ゆくいちにち富士のそばにゐて
八十八夜 (浜松)渥美 絹代
まむし草活け風音のにはかなる
山羊の仔を撫でて八十八夜かな
遡上せる鮎に鉄橋響きをり
桐咲いて入り日大きくなりにけり
母の日や山に夕日のまだ残り
田を植ゑてより初めての雨の音
ささくれを剝がし卯の花腐しかな
緑さす一枚板のけやきの戸
嘴太からす (唐津)小浜 史都女
水苔のふはつと五月来りけり
水の香の真昼濃くなる蓮若葉
蓮浮葉風を捉へて動き出す
十薬の葉裏真つ赤や走り梅雨
人語より鳥語親しき五月晴
彫刻の森にうぐひす老いを鳴く
この星に八十余年豆御飯
おし黙る嘴太からす南風
姫女菀(宇都宮)中村 國司
余花落花江戸ふり返る曾良の像
薔薇蕾開かんとしてこつち見る
請負の男子ばかりの田植かな
鴨と鷺目と目合はさずゐる薄暑
風呼ばず自他をゆらさず九輪草
夕焼に供ふるぐんかんのマスト
せんせいに出自を問はれ姫女菀
タクシーの社名も薫る帰省かな
新緑 (東広島)渡邉 春枝
新しき句帳を開く花の園
木の匙に残る木の香やあたたかし
散るさくら追ひかけて行く三歳児
名園の池を一周散るさくら
初蝶の後円墳の真中より
のら猫に名前授くる子供の日
新緑や歩きながらのメール打つ
海の日に届く絵文字のメールかな
知床 (北見)金田 野歩女
春霞ゆつくり湖に溶けてゆく
対岸の灯は出湯の宿朧月
姉卒寿足取り軽く胡瓜蒔く
知床に蝦夷赤蛙響きをり
ハンカチの木の花図鑑よりも美し
青東風や牧夫撫でをる馬の首
清流の花藻水玉模様めく
二歳児のママでなくては夏帽子
南吹く (東京)寺澤 朝子
久々に歩む川筋柳絮舞ふ
初夏や街を貫く水戸街道
新樹蔭ノート開けばさみどりに
紫蘭咲く夫在りし日の散歩道
青い目の人形寝かせ籐寝椅子
男衆の角帯確と祭前
祭笛路地から路地へ猫通る
足早に晩年来るよ南吹く
菖蒲湯 (旭川)平間 純一
日を纏ひ飛花や落花の阿弥陀仏
夫婦なる木墓寄り添ふリラの雨
柳絮飛ぶ木墓にありぬ魔除け紋
春蟬や朽ちゆくばかりビッキ墓碑
菖蒲湯やわんぱく坊主丸洗ひ
五月田に特急列車滑り行く
水楢の青葉そよげるアイヌ墓地
えごの花墓終ひする話など
夏の月 (宇都宮)星田 一草
水白き渓になだるる藤の花
若鮎の遡上雪嶺を遠くして
作務衣着て寺門前の茶摘かな
チューリップ赤きワインを注ぎたし
筍に何の咎ある斬首かな
エンジンを休め田植の小昼飯
牛小屋の牛顔を出す夏の月
十薬の偽りのなき白さかな
|
夏の月 (栃木)柴山 要作
眼癒え積ん読に手が若葉風
薔薇の咲きしばし王者のごとき日々
東の果ては筑波嶺麦熟るる
青葉風神鼓どよもす一の宮
街騒を眼下に涼し蕪村句碑
十薬に翼の生るる夕まぐれ
大鳥居にかなふ茅の輪や野の匂ふ
見世蔵の甍の波を夏の月
麦の秋 (群馬)篠原 庄治
履初めの靴が足喰ふ花の旅
庭の隅稚児百合ゆるる影持たず
葭切の鳴き移りつつ葭を出ず
上州の平野彩る麦の秋
梅雨入となりたる今朝の雲厚し
廃校舎閉ぢし門柱梅雨滂沱
ほととぎす風に乗る声風が消す
赤城山裾なだらかに麦の秋
灯台へ (浜松)弓場 忠義
灯台へゆく道ひとつ夏に入る
出航の漁船になびく鯉のぼり
闘病を笑うて暮らす古茶新茶
墨壺の真綿の乾く三尺寝
新樹の夜路上ライブの輪の中に
水門の開けられてをり花いばら
竹の皮脱ぎ捨てらるる午後の闇
雨蛙尊徳像の薪の上
風を味方に (出雲)渡部 美知子
初夏の風を味方に六千歩
大粒の苺を口に電話とる
瑞垣に沿うてくるくる白日傘
薫風や骨董市をふた巡り
せせらぎの音に乗りくる新樹の香
夏めくや手に銅矛のずつしりと
朝風のささやき合へる植田かな
夏のれん割つて二人の指定席
煤の跡 (出雲)三原 白鴉
麦秋や土器に煮炊きの煤の跡
遺跡への道はひとすぢ椎若葉
たかんなや竹林にある狭き空
蔵人の紺の前掛け夏燕
植田渡る笛は先触れ伊勢神楽
亀の子の四肢ばらばらに泳ぎけり
昼顔や浜に錆つく巻揚げ機
貫入の音の間遠に夏の月
杉菜抜く (札幌)奥野 津矢子
杉菜抜く朝のあいさつ交はしつつ
風よろし肺の奥までリラ吸うて
筍を剝くどこまでと決めもせず
墓標とも見ゆるビル街夏霞
噴水は子供の夢の高さまで
啄木碑までの坂道九輪草
夏の蝶草に沈んでゆくところ
潮の香に途中下車する夏帽子
口笛 (宇都宮)星 揚子
甕の蝌蚪三ミリほどの尾を振れり
運転手声を明るく更衣
口笛に犬呼び戻す麦の秋
寺町に餃子の匂ふ薄暑かな
腹筋の割るる仁王や青嵐
慈光寺の粒の揃へる蛇苺
走り梅雨足の指反る大師像
くるりと蟻仏足石の文計る
麦の秋 (浜松)阿部 芙美子
集落といへども三戸麦の秋
母の日や姉がますます母に似て
花束の白き薔薇より萎れゆく
更衣杖の代りの男傘
新茶淹る節榑立てる男の手
何気なき日々どくだみの匂ひけり
梅雨晴の香る柾目の檜風呂
数多付箋付けたるままに曝書せり
汀 (浜松)佐藤 升子
仕舞屋となりたる鍵屋花みづき
はつなつの汀を走る波頭
新緑や触るれば熱き馬の首
滑り台の着地は砂場若葉風
風薫る小学校に木のポスト
一つ失せたる白服の貝釦
吐く息の始め大きく水中花
杭に干す漁網一枚蒲の花
|